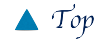🔍 古事記の秘密を解き明かす、神名と伝説の由来
おや、子どもたちだけで、この土地ん言い伝え聞きぃ来たかいな。 えらい関心やわ。 子供のためのやさしい『古事記』 の続きを聞きたいって? ほな、そこ座って、おばあちゃんの話聞きな〜。 今まで聞いた話は…… 【あらすじ】・ 宇宙は混沌とした《渦》だった ・ 高天原に三柱の神(造化三神)が生まれた ・ 続いて、二柱の神(ここまでが別天津神)が生まれた ・ 次に、五組十柱の神々(神世七代)が生まれた ・ イザナギ&イザナミの神様が伝説の島を作った ・ 黄泉の国のゾンビから逃げて、川で身体洗って ・ わめくスサノオが天界に来て姉弟バトル天照大御神 様と、素戔嗚尊 様の対決の話までとな……。 でもなぁ、素戔嗚尊 様んこと『悪ガキ』や言うて、バチ当たらんといいけどなぁ。あの方もなぁ。 ・ ・📓 古事記上巻-7 素戔嗚尊の奇行
・ ・『古事記』上巻(素戔嗚尊の騒動) 「従正五位上」官位 太 安万侶 (奈良時代)
じゃあ村の外れのばあちゃんが、この土地の古くからの話をしような。 子供達が聞いた、あの姉弟対決で交換した話の続きやな。 この国には昔な、天照大御神 いう、とっても立派な神様がおったんやで。 天照大神 様はな、三人の女神様を生み出してん。 伊勢の地のでっかい神殿の…… ・ 奥津宮 の 多紀理毘賣命 ・ 中津宮 の 市寸嶋比賣命 ・ 邊津宮 の 田寸津比賣命 胸形君って人がおるやろ? あの方のご先祖様やねん。 ・ ・ 反対に、素戔嗚尊様 が生み出した男神の子孫は、 天菩比命 の子どもの、建比良鳥命 は、 その子たちが 出雲国造 や 武蔵国造 などのご先祖様とされてるんや。 それと、天津日子根命の子孫には、 川内国造 や 額田部湯坐連 などもおるんやで。 素戔嗚尊 様はな、自分の子どもたちのほうが、姉上の女神たちよりも優秀や言うてはりましたけど、実際のトコロ、子どもはともかく、彼自身の行動は乱暴で、天照大神 の畑を荒らしたり、大嘗祭 の殿で暴れたりしてたんやと。 天照大神 の織ってた布を破壊したときなんて、織女が驚いて死んでしまったほどやとか。 そないなことされたら、天照大神 様もお怒りになるわな。結局、素戔嗚尊 様は天界から追放されることになったんや。 ・ ・ この話はまだまだ続くけど、今日はここまでにしとこうか。 なんでも、いったんココで【解説】を入れたいそうなんですわ。 また次の機会にばあちゃんが続きを話すな。📓 素戔嗚尊の奇行の解説!
実はこの、〝スサノオ〟とされる人物の奇行は、完全な作り話ではなく、モデルとなった事件がある。 【大祓詞】本当にそのように暴れ回った王子が存在し、彼の奇行が、後に支配側に就く者達の戒めとなるよう、わざと不名誉な記録がこのような形で【大祓詞】に載せられた。 学校で言うなら、天の益人等が 過ち犯しけむ 種種の 罪事は 天津罪
王子君が、ここでバットを振り回して、壁に穴を空けちゃいました! この壁の穴は、王子君のせいです!
と、大穴の横に 『不名誉な看板』 を建てられてしまったようなモノ。 王子君卒業後も、その不名誉な記録だけは永遠に残り、後に入学してくる生徒達の戒めになる。 【初代天皇からの警告】王子がバカみたいにバット振り回してな、壁に大穴空けてもーた! こんなんもう直らへん! もう芸術作品したるわ! デカデカと〝この穴の作者は王子君です〟って書いといたるわ!!
ちなみに、大嘗祭とは新天皇が即位して最初の新嘗祭のことなので、モデルとなった人物の一連の事件の裏には「地域住民の五穀豊穣の妨害」という意図が感じられる。ほんま、アホなことしたら、お前もコイツみたいこの『看板の刑』なるで! 豪族も貴族も関係ないわ。羽目外さんと気いつけい!
用語解説ちなみに、モデルとなった事件に関しては、『古語拾遺』ではもっと詳しい。 このように『古事記』は、『神話』のような形を採用しながらも、実際の事件が混ざり込んでいる。 いや、実際の事件を、『神話風』に記録したと言うべきだろうか??(伏線) その答えは、読み進めていくウチにどんどん明らかになりますが、ところどころ、このような形で『謎解き』のヒントを出しながら、先に進みます。 『古語拾遺』の話はまた後ほど。新嘗祭って何ですか? 天皇が国民を代表して神々に感謝を捧げる儀式として、毎年11月に天皇がその年に収穫された新米を神々に捧げる儀式。五穀豊穣と国家の繁栄を神に感謝し、祈る目的で行われる。
初心者が楽しく読める古事記入門8−天照大神の天岩戸隠れ